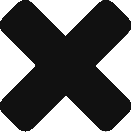いよいよ決まった保育園
横浜市は今週保育園の利用認定通知が届きますね。ドキドキですね。
私の元にも、私が関わらせていただいているお母さんたちから少しずつご連絡をいただいています。
利用が決まっても「これでよかったのか」とそわそわ悲しくなり、決まらなかったら決まらないで悲しくなり・・。
最初からこの春に保育園利用を決めていないご家庭も、周りに仕事復帰していく方がいて・・となってくると何かしらそわそわしますよね。
・
その状況、とってもよくわかりますよ。
わたしも10年以上前そんな一人の母親でしたから。

保育園決定=断乳と思わなくてよい
保育園が決まって仕事復帰が現実的になった時、
【断乳した方がよいでしょうか?】
【哺乳瓶に慣らせた方がいいでしょうか?】
こんな質問を毎年お母さんたちがよくしてくださいます。
・・結論ですが、
≪どちらも必要ありません≫
私はそう思っています。
「え???」って思う方もいるかもしれませんね。
もちろん、各ご家庭、月齢、お子さんの今の様子、色々条件が違います。
お母さんの仕事形態だって、通勤時間だって、みんな違う。
どのくらいの時間保育園に預けるか、もみんな違う。
・
・
だから、「絶対こうしないといけない、こうしたほうがいいよ」ということは一律には言えません。

・
ちなみに、「卒乳」というのは「子どもが自らおっぱいを卒業していくこと」であり、
「断乳」というのは「(子どもはまだ欲しがっているけれども)親の意思でおっぱいをあげることを断つこと」です。
・
・
我が子が生まれてから今日まで、お母さんが100人いれば100人それぞれの色々なシチュエーションがあります。
お母さんの想いに反してお子さんが想定より早く「卒乳」していった状況もあれば、本当はおっぱいをあげたかったけれど何かしらの理由で早々に「断乳」をする必要があった状況もある。
逆にお母さんは「食事もよく食べるし、早く子どもに卒業してほしいけれど、でもいつまでもおっぱい飲んでいるんですけれど!」「おっぱいがないと寝れなくて、まだなくせない」というシチュエーションもあるかもしれません。
・
・
ただ、「仕事復帰=断乳」の一択とは思わなくていいですよ。
・
なぜならば、実は復職時に母乳を細々とあげていくメリットは山ほどあり、国際的にもたくさんのエビデンスが出ています。
母乳は量依存性でして、細々あげ続けることにより、病気への罹患率・重症化率などが有意に下がり、また母親の子どもの看病のための休暇取得の日数も減ることがデータから分かっています。
(保育園にいったら、ま~~~~これ最初はお熱、お風邪のオンパレードです!そうやって我が子は強くなっていくんですけれどね。)
そして、これまでずっと一緒にいた親子がそれぞれ「職場」と「保育園」と別々の社会に出ていくとき、母親もですが我が子にも少なからずストレスはかかるわけです。
そんな時に「授乳」という「変わらないもの」は親子の支えになりうるでしょう。
あ、もしすでにもう「今おっぱいは飲んでいないよ」っていう親子さんは、よりいつもよりハグハグハグ!したりたくさんスキンシップとってあげてくださいね♡
お子さんとっても安心すると思いますよ♡

慣らし保育中に「慣らしおっぱい」ができる
具体的には、慣らし保育中に「慣らしおっぱい」ができます。
預け時間が少しずつ延びていくにつれおっぱいも少しずつ貯められるようになり、慣らし保育が終わるころには日中全くおっぱいをあげなくても保てるようになります。
そしていざ仕事復帰して、朝家を出る前、帰宅時、夜寝る前だけのおっぱいでも ちゃんと産生され、トラブルを起こすことなく、その後お子さんの成長とともに卒業していく、ということは十分にできるようになるんですね。
哺乳瓶の問題も、子どもの成長によりうまくいかないこともありますし、お母さんがいない環境に慣れた時にできることもあります。
・
・
もし、仮に「そんなこと言われたって、私は絶対無理だから復帰までに断乳したい!」という場合は、
助産師とスケジュールを組んで作戦立ててやっていくことが必要です。
その場合は、私であれば、その頃のその方のおっぱいの回数や生産量にもよりますが、予定を合わせた状況で授乳をやめて3日後、1週間後、状況でそこから数週間後に1回という形で、わざと溜めたおっぱいを排乳させていただくケアをして、完了していきます。
・
いや、「卒乳にしたいけど、慣らし保育中に回数も減って不安だから診てほしい」もあるかもしれません。その時もおっぱいの状況を拝見しながら、今後どのようにおっぱいを続けながら保育園と仕事とやっていくのがよさそうか、一緒に方針を立てていきます。
・
「卒乳」「断乳」どちらもいくらでも拝見します。
・
「仕事復帰が決まったからこうしなければならない」ではなくて、今のお母さんご自身の気持ち、お子さんの様子をみながら、現実的にできそうなところを探していけるといいですね。
もし必要な時は、いつでもご相談に乗りますのでお声がけしてくださいね。(下の写真は0歳から保育園に行っている2歳さんの写真です♡)